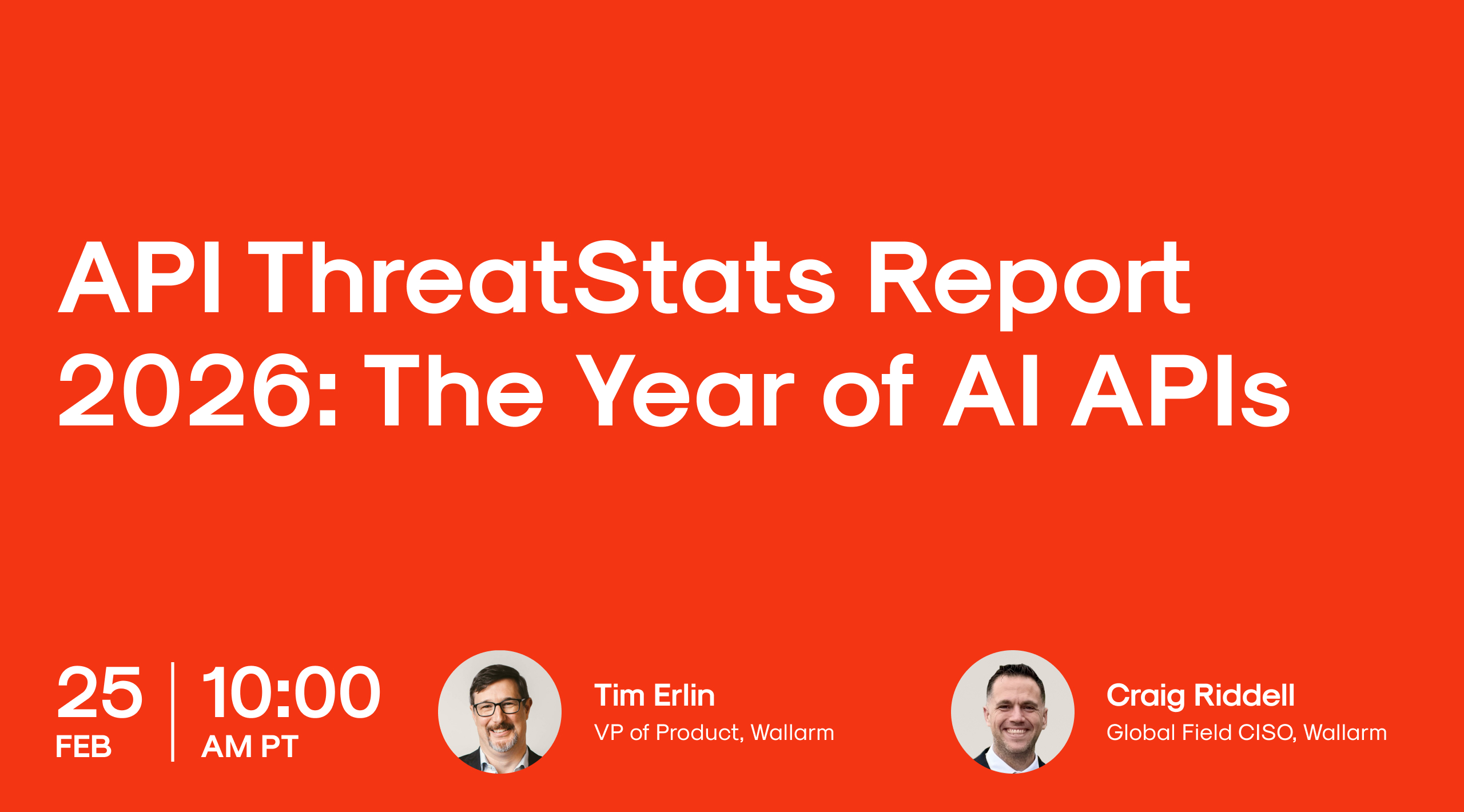統合インフラとは? Wallarmガイド
数多くの企業が、配置モデルのモジュール化とITスタックの効率化を望んでいます。そのため、不要な仕組みを排除して構造を簡素化する統合インフラが求められます。

非統合インフラとは?
統合型アーキテクチャとは異なり、非統合型ネットワークでは、貴社や雇ったコンサルタントが個々のハードウェア部品を調達し、組み合わせる必要があります。ネットワークを介して接続されたこれらのサイバースペースは、ハイパーバイザーを動かし、コンピュータの仮想化を実現し、情報をSANまたはNASに保存いたします。
統合インフラ(CI)とこのアーキテクチャにはいくつかの共通点がございますが、主な違いは、CIが1社によってあらかじめ統合されている、または複数のベンダーが共同で作り上げた方式に基づいている点にあります。
統合インフラとは?
統合インフラは、サーバ、ストレージ、ネットワーク、管理ソフトなど、複数の部品がひとつとなって動作する仕組みです。各種ハードウェアやソフトウェアを複数の供給元から購入する代わりに、企業は通常、これらのシステムを1社から導入いたします。
データセンターを構築する際、統合インフラ技術はあらかじめ設定・検証されているため、導入がより簡単かつ迅速になります。
統合インフラはどう動く?
統合インフラは、さまざまな方法で実現することが可能です。ベンダーが検証したハードウェアリファレンスアーキテクチャを採用する、単体アプライアンスをクラスタ化して構築する、またはソフトウェア主導のハイパー統合型方式を選ぶなどの手法があります。
統合インフラのリファレンスレイアウトを活用することで、データセンターの負荷をより正確に割り当てることができます。各コンポーネントを最大限に活用するため、各ベンダーのリファレンスレイアウトを参考にしていただけます。

統合インフラの利点と欠点
統合インフラは、多くの場合、1社の製品を利用します。
CIに関連する利点は以下の通りです:
- 互換性の向上: ハードウェアとソフトウェア間の非互換性を減らす、もしくは解消するのに役立ちます。
- コスト削減: 統合技術により、データセンターの準備、導入、管理の費用が抑えられます。各システムは、同一ベンダー由来であっても、専用の管理ツールを必要とする場合がある中、IT部門は一元的なインターフェースでリソースを監視できるようになりつつあります。
- 簡素化: 複数メーカーの機器に精通する必要がなくなるため、データセンターの管理が容易になります。
一方で、以下のような欠点も考えられます:
- ベンダー依存: CIは1社に依存するため、機能面や拡張性に制限が生じる可能性があります。
- 複雑かつ高価: 導入後のコンポーネント追加が困難になる場合がございます。
統合インフラ vs ハイパー統合インフラ vs 構成可能インフラ
ITソリューションの管理には、統合、ハイパー統合、構成可能なインフラなどの手法があります。CIとHCIは、従来のインフラの区画的な運用を解消し、効率的な連携を目指す点で共通していますが、HCIはハイパーバイザーのレベルで実現され、複数ノードのクラスタによって共有リソースプールを構築します。
構成可能インフラは統合が目的ではありませんが、ITリソースは同様に物理的な場所から抽象化され、ウェブ上で管理できるようになっています。
統合インフラの導入方法
CIは、主にリファレンスデザインまたは既にラックに組み込まれた構成という2つの方法で導入されます。
- リファレンスアーキテクチャは、検証済みのベストプラクティスに基づいた設計図であり、統合システムリソースの設定、範囲、相互依存関係を示します。この方法により、迅速な導入と既存機器の活用が可能となり、各ベンダーの設計図に記された仕様に従って計算、ストレージ、ネットワークリソースの割り当てが行われます。対応するアプリの管理者は、各コンポーネントの配置数を容易に増減できるため、柔軟な運用が可能です。
- 既にラックに組み込まれた構成は、計算、ストレージ、ネットワークの各部品が揃っている状態です。部品は先に配線・接続済みで、起動が容易になるよう整えられています。この方法は導入をさらに迅速化しますが、通常はスケールアウト方式のみをサポートします。
統合インフラのベンダー
ほとんどの従来型ストレージプロバイダは、直販またはチャネルパートナーを通じて統合インフラ製品を提供しています。対象例:
- Atlantis ComputingのHyperScaleノード(フラッシュメモリ搭載)。
- CiscoのHyperFlexは、Cisco UCSサーバ上でSpringpathを統合。
- Dell EMCのVxRack SDDCシステムおよびVxRail(HCI)は、Dell EMCの製品群に含まれる。
- HPE Converged System。
- HPE SimpliVity HCIは、HPE ProLiantサーバを使用。
- Hitachi Unified Compute Platform。
- IBM VersaStackは、Cisco UCS、Ciscoネットワーク、IBM Storwize V7000アレイで構成される。
- NetApp FlexPodは、Cisco UCSサーバとスイッチングを利用。
- Oracle Cloud Converged Storageは、Oracle ZFSアレイと一般ハードウェア上のVMware vSANを用いる。
結論
多くの方がCIについて語り、考えています。ハードウェア界隈の資料は、「統合コンピューティング」、「ファブリックベースコンピューティング」または「ダイナミックフレームワーク」と呼ばれる場合もあり、その数は実に多岐にわたります。要するに、統合インフラとは、1つの筐体内に複数のサーバ、ストレージ方式、ネットワークノード、インフラ管理ソフトが搭載された仕組みです。
FAQ
参考資料
最新情報を購読